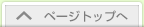学校建設の概要
アジアの経済的発展が著しい一方、ベトナム・ラオス・タイの山岳地帯に居住する多くの少数民族は発展から取り残され、格差が広がる一方です。道路・水道・電気・医療・学校など基本的な生活基盤も未だ整いません。
教育セクターにおいては、学校数も絶対的に不足している状況で、たとえ校舎があっても老朽化が進み荒廃したものも多く、屋根が傷んで雨漏りがしたり、壁が崩れたままであったり、トイレが設置されていない学校もたくさんあります。校舎のみならず教員や教材も不足し、教育環境は劣悪な状況です。
少数民族の児童はそれぞれの民族の言葉を話し、学校で初めてそれぞれの国の公用語を学びます。言葉の壁から授業についていけずにドロップアウトしてしまう、家が貧しいために学校を続けられない子供もたくさんいます。現在、アジア教育友好協会はこのような地域での学校建設と、学校プロジェクトを通して教育への理解と村の発展を推進する活動をしています。
ベトナム
17世紀の朱印船貿易以降、日本とは歴史的に強いつながりをもつベトナム。2013年には日越友好年(国交樹立40周年)を迎え、両国の関係はますます深まっています。親日国として知られており、都市近郊の工業団地には数多くの日本企業が進出しています。しかし、近年、都市部では高い経済成長を実現する一方、山岳・高原地帯に居住する国民の約13%を占めている53の少数民族の中には、未だ貧困に苦しんでいる地域もあり、その格差が問題となっています。
AEFAが支援をしている中部高原はベトナム戦争の激戦地でもあり、少数民族が数多く居住している地域。インフラの整備は遅れ、現在でも村の集会所や倉庫などを間借りして授業を受けている子ども達がいます。国平均の初等教育就学率が95%を超える一方で、現実には70%程度にしか達していない地域もあります。また、学校に在籍しているものの、実際には親の手伝いをするために欠席したり、ドロップアウトしているという現実も少なくありません。また、中部の山間部は水害や台風などの被害を受けやすく、農業での自給自足の生活も厳しい状況です。
AEFAでは学校という建物を建設するだけでなく、子ども達の教育環境を整える奨学金プログラム、少数民族の子ども達が日本の学校とつながり自分達の文化も大切にできるような交流プログラムを推進しています。また、今後は授業の質を高めるための取り組みなどに実施していきます。
- パートナーNGO:
- Health and Education Volunteers
- Saigon Children's Charity
- Research & Communication Centre for Sustainable Development
ベトナムの建設校 (ベトナムの建設校の詳細はこちらです)
| 地域 | 省名 | 建設数 | 地域 | 省名 | 建設数 |
| 北部 |
ランソン省 タイグエン省 トゥエンクアン省 フートュー省 タンホア省 ゲアン省 ホアビン省 フーイェン省 イエンバイ省 ソンラ省 バクザン省 |
1 6 19 2 2 1 1 1 2 2 2 |
中部 南部 |
クァンチ省 クァンビン省 フエ省 クアンナム省 コントゥム省 ダックラック省 ダナン市 ヴィンロン省 チャビン省 タイニン省 ドンナイ省 |
2 1 3 30 54 11 3 1 9 2 3 |
| 合計 | 158校 | ||||

ラオス
インドシナ半島唯一の内陸国、ラオス。最近では癒しの国として世界遺産や仏教遺跡をめぐる旅行者が増え、工業団地に日系企業も進出しています。その一方で、人口の65%を超える少数民族は、経済発展から取り残され貧困の生活を余儀なくされています。
南部サラワン県の山岳地帯には少数民族が多く居住し、不発弾や枯葉剤等ベトナム戦争時の爪あとが未だに深く残る地域です。土壌が痩せており、また不発弾が残ることから耕地も少なく、米の自給率は3-6ヶ月と村の生活は貧しい状態です。行政の力も弱いため、水道・電気のインフラも整わず、まず食べるための農業や食料集めが優先され、教育を受けていない子供が60%に達しています。ラオスの義務教育は小学校までですが、このような地域では学校がないために大人でも民族の言葉しか知らず、ラオス公用語であるラオ語を理解する者は5~20%程度です。
AEFAは、小学校だけでなく、少数民族の子供たちがまず言葉の壁を越えるため就学前教育(幼稚園)の支援や、小学校卒業後の道をひらくための中学校建設、少数民族出身の教員を育てるための奨学金など、村・学校とともに継続した取り組みを協働しています。
ラオスの建設校 (ラオスの建設校の詳細はこちらです)
| 地域 | 省名 | 建設数 |
| 北部 南部 |
ビエンチャン県 サラワン県 チャンパサック県 |
4 63 25 |
| 合計 | 92校 | |

タイ
タイと日本の歴史は15世紀までさかのぼり、現在も強いつながりを持つ国です。
経済的発展が著しい一方、北部山岳地帯には、カレン族など十数部族、約75万人の少数民族が生活しています。多くは中国やミャンマー、ラオスからここ1~2世紀の間に移住してきた人々で、伝統的な文化と生活様式を大切にして生活してきました。しかし、北タイは気候の厳しさに加え土地がやせて貧しく、さらには近年の森林資源保護政策により伝統的な焼き畑農業が制限され、生活はますます厳しくなっています。貧しさから都市部への出稼ぎによる家庭・コミュニティ崩壊、HIVの感染などの問題も深刻になっています。
タイの義務教育は中学校までで、データ上は初等教育の就学率は100%となっていますが、実際にはこのような地域では学校に行きたくても行けない子供が多く取り残されています。
AEFAはパートナーNGOと共に、少数民族としての伝統も大切にする学校プロジェクトを推進しています。
- パートナーNGO:
- Raks Thai Foundation / Care Thailand
タイの建設校 (タイの建設校の詳細はこちらです)
| 地域 | 省名 | 建設数 |
| 北部 |
チェンマイ県 プア県 |
13 1 |
| 合計 | 14校 | |

中国雲南省
雲南省の高地には、25の少数民族が厳しい自然環境下で生活し、経済的に取り残された地区が数多くあります。風雨から身を守り災害にも耐える安全な学校、トイレ・井戸などがある、衛生面でも安心できる学校が不足しています。
中国雲南省の建設校 (中国雲南省の建設校の詳細はこちらです)
| 地域 | 省名 | 建設数 |
| 西部 | 雲南省 | 2 |
| 合計 | 2校 | |

スリランカ
絶大な親日国のスリランカの国土面積は北海道の8割程度の広さです。そこには多数の民族集団が存在しており、大都市の学校を除く地方の多くの学校ではシンハラ語のみ、またはタミル語のみの授業しか行われていないため十分に意思の疎通を図ることが困難で、26年間に及ぶ民族紛争の一因になったとも考えられます。この内戦も2009年に終結し、政府はその大きな傷跡を修復しつつ教育に力を入れていますが山間部や僻地での学校施設を充実する余裕がないのが実情です。またこのような地域には貧困家庭が多く、子供を就学させることができない家庭も少なくないのです。そのためスリランカ全体の識字率は92.5%とアジアの国の中でも高いにもかかわらず山間部や僻地では6.5%と大変低い所があります。
このような教育環境の行き届いていない山間僻地の地域ではキリスト教や仏教などの宗教団体が宗教の枠を超えて複数の言葉を使用する教育を施し、子供たちのみならず、教育を受けることができなかった成人にも教育の機会を与えるため支援の手を差し伸べています。
AEFAはこれらの宗教団体を支援しスリランカ南部の山間部に学校建設をしています。
- パートナーNGO:
- ダヤシリ・ワルナクヤソーリア氏
| 地域 | 建設数 |
| 南部州 | 3 |
| 西部州 | 1 |
| 合計 | 4校 |